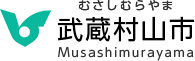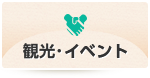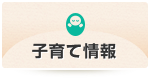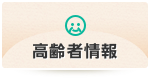要介護・要支援状態の認定申請から認定まで
1 申請
申請方法
介護保険のサービスを利用するには、「介護予防・日常生活支援総合事業」のみを利用する場合を除き、介護が必要な状態(要介護状態又は要支援状態)の認定を受けることが必要です。
認定を受けるためには、介護保険の被保険者証を添えて高齢福祉課窓口に申請してください。郵送でも受付けています。
郵送の場合は、申請書の到達日が申請日となります(申請書の内容に不備があった際は、到達日に受付けられないことがあります)。
- 申請は、本人又は家族のほかに指定居宅介護支援事業所や介護保険施設に代行してもらうことができます。
- 介護保険のサービスを利用したいけれど、介護保険の申請手続きの方法がわからないかたは、お住まいの地域を担当している地域包括支援センターで相談しながら申請を代行してもらうこともできます。
- 当面、介護保険のサービスを利用する予定のないかたは申請の必要はありません。必要になったときに申請してください(急にサービスが必要になった場合は申請日から使うことができます)。
郵送の際の送付先
〒208-8502
武蔵村山市学園4-5-1
市民総合センター内高齢福祉課介護認定給付係
(注釈)下記のエクセルファイルは、複数のシートで構成されています。ご確認ください。
申請の取下げ
認定が出る前に、介護サービス利用の必要がなくなるなどの理由で要介護・要支援認定を受ける必要がなくなった場合は、申請を取り下げることができます。その際は、申請取下書の提出が必要です。
(注釈)下記のエクセルファイルは、複数のシートで構成されています。ご確認ください。
更新申請・区分変更申請について
更新申請
サービスを継続して受けたい場合は更新申請が必要です(事前に市から更新のお知らせをお送りします)。 申請から認定まで1か月以上かかる場合もあるので、ご了承ください。
変更申請
心身の状態が大きく変わったときは、認定の変更申請を行うことができます。 現在介護サービスを利用しているかたは、申請する前に担当のケアマネジャーと相談してから申請してください。
新規・更新・変更ともに申請の手続きは同じです。
2 要介護認定
申請者が、介護が必要な状態にあるか、あるとすればどの程度かの認定をします。この認定を要介護・要支援認定といいます。
要介護・要支援認定の基準は全国一律に決められています。
認定されるまでの流れ
1.認定調査
市職員又は市から委託を受けた調査員がご自宅等を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて、調査を行います。
入院や手術の直後など、心身の状態が日頃と異なる場合は、調査に伺うまでに時間を要する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
調査日時は事前に調査員から本人またはご家族に連絡をしますので、平日の日中で都合のよい日時を決めてください。土日祝日の調査は行っておりません。
2.主治医の意見書
市が直接、主治医(かかりつけの先生)に意見書の作成を依頼します。
主治医は病気や負傷の症状等をまとめた医学的な見地からの意見書を作成します。 受診の頻度が少ない場合や、主治医の診療科目によっては、意見書の作成ができない場合もありますので申請する前にあらかじめ主治医の先生にご相談ください。
主治医がいない場合には、市が紹介する指定医の診断を受けていただきます。
3.一次判定
認定調査の結果や主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
4.二次判定(介護認定審査会)
一次判定の結果や認定調査時の特記事項、主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門職で構成する介護認定審査会で、どのくらいの介護を必要とするかの区分を審査判定します。
3 認定結果の通知
市は介護認定審査会の審査判定の結果に基づき、要介護・要支援認定及び有効期間(3か月から48か月)を決定し、通知します。
申請から認定結果の通知までは、原則30日以内に行われることになっていますが、場合によっては1か月以上かかることもあります。
認定の区分
認定は、要介護度に応じて下記のような区分に分けられ、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。
1.要介護状態の区分が要介護1から要介護5のとき
介護サービスが受けられます。
2.要支援状態の区分が要支援1・要支援2のとき
今よりも身体機能が低下しないように介護予防サービスが受けられます。
3.非該当のとき
認定の結果が非該当と判定された場合でも、基本チェックリストにより総合事業該当者と判定された場合は、「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用できます。お住まいの地域を担当している地域包括支援センターまでご相談ください。
認定結果に不服がある場合には、東京都の「介護保険審査会」に申し立てができます(受付窓口は東京都になります)。
ご存知でしたか?要介護認定を受けているかたの「所得税控除について」
障害者控除対象者認定
65歳以上で、身体障害者手帳等の交付を受けていないかたであっても、要介護認定を受けているかたで、身体状況や認知症状が一定の基準を満たしているかたついては、「障害者控除対象者認定書」という書類を発行します。この適用を受けるには、事前に高齢福祉課へ申請する必要があります。
この書類を税の申告時に提出することで、「障害者控除」の対象となります。ただし所得税又は住民税が非課税のかたは対象になりません。
おむつ費用の医療費控除
要介護認定を受けているかたで、医師から治療上おむつを使用することが必要であると認められたかたは、医師の発行する「おむつ使用証明書(発行は有料の場合があります。各医療機関にお問い合わせください)」を添付して、その費用(紙おむつの購入費用及び貸しおむつの賃借料)について医療費控除を受けることができます。おむつ費用に係る医療費控除を受けるのが2年目以降のかたで、身体状況について一定の基準を満たしているかたについては、この証明を高齢福祉課が発行する「おむつ使用に係る主治医意見書確認書」という書類で代用できる場合がありますのでご相談ください。
令和6年以降に使用したおむつ費用について
令和6年分より、医療費控除を受けるのが1年目のかたでも、高齢福祉課で発行する「おむつ使用に係る主治医意見書確認書」をもって控除が受けられるようになりました。その際、1年目のかたと2年目以降のかたで要件が異なりますのでご注意ください。
- 1年目のかた おむつを使用していた年に受けていた要介護認定及びその認定を含む複数の要介護認定の有効期間を合算して6か月以上であり、その際に作成された主治医意見書の内容が一定の基準を満たしていること。
- 2年目以降のかた 要介護認定を受けており、おむつを使用していた年に主治医意見書が作成されていること。その年に主治医意見書が作成されていない場合は現に受けている介護認定の有効期間が13か月以上であり、その際に作成された主治医意見書の内容が一定の基準を満たしていること。
サービス利用時の自己負担額の医療費控除
訪問看護などの医療系の居宅サービスを利用しているかたは、当該居宅サービスに係る自己負担額(保険給付の対象となる自己負担額に限る)が、医療費控除の対象となります。また、特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所しているかたも、介護費に係る自己負担額、食事に係る自己負担額及び居住費に係る自己負担額として支払った額(支払った額の一部)が医療費控除の対象となります。
1.自己負担額が医療費控除の対象となるサービス(以下表1・2のとおり)
表1
| 医療費控除の対象となる介護保険サービス |
|---|
| (介護予防)訪問看護 |
| (介護予防)訪問リハビリテーション |
| (介護予防)居宅療養管理指導 |
| (介護予防)通所リハビリテーション |
| (介護予防)短期入所療養介護 |
|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る) |
| 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護を除く)に限る) |
表2
| 表1のサービスと併せて利用した場合のみ控除対象となるもの |
|---|
| 訪問介護(生活援護中心型を除く) |
| 夜間対応型訪問介護 |
| (介護予防)訪問入浴介護 |
| 通所介護(地域密着型を含む) |
| (介護予防)小規模多機能型居宅介護 |
| (介護予防)認知症対応型通所介護 |
| (介護予防)短期入所生活介護 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る) |
| 複合型サービス(表1の居宅サービスを含まない組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護を除く)に限る) |
| 地域支援事業の訪問型又は通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く) |
2.特別養護老人ホームに入所しているかた
自己負担額の2分の1の額
3.介護老人保健施設・介護医療院に入所しているかた
自己負担額の全額
4.留意事項
(注)1の自己負担額は介護費負担額、2・3の自己負担額は介護費・食費・居住費負担額の合計を指します。
(注)医療費控除を受けるためには、当該支払いをした領収書が必要です。紛失した場合等は、利用した施設等にご相談ください。
介護保険被保険者証等の再交付について
介護保険被保険者証等を紛失された場合は、以下の申請書に記入し、高齢福祉課の窓口に御提出ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部高齢福祉課介護認定給付係
電話番号:042-590-1233 ファクス番号:042-562-3966
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。